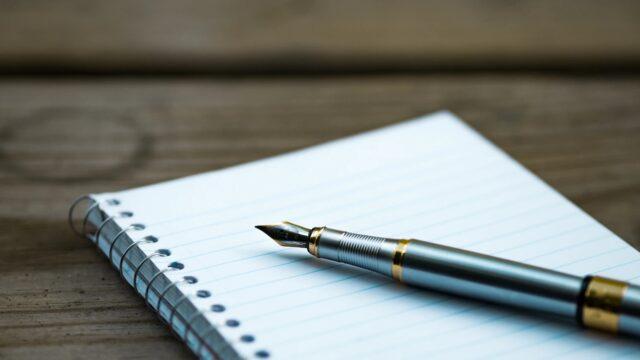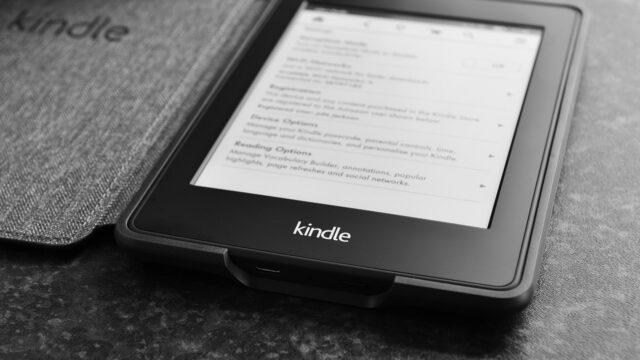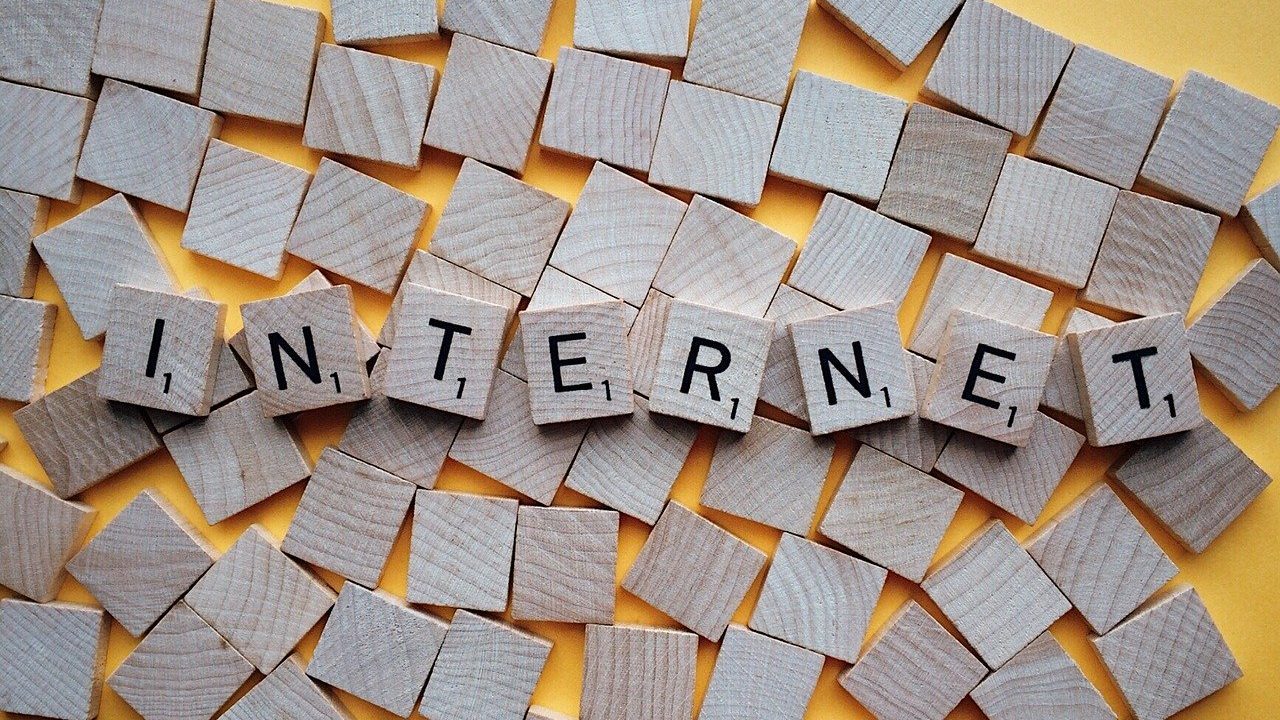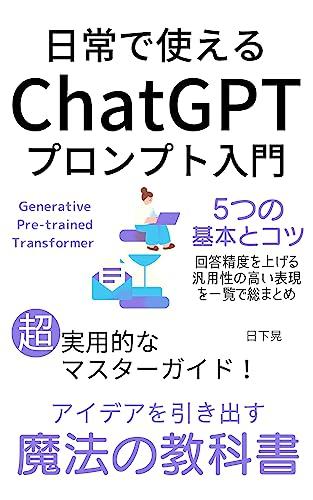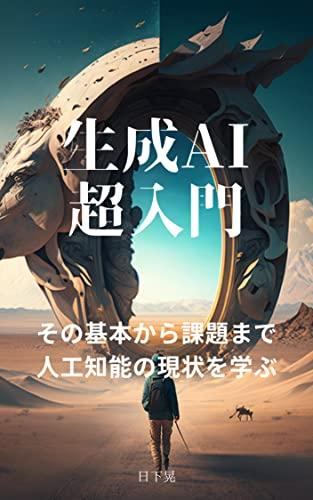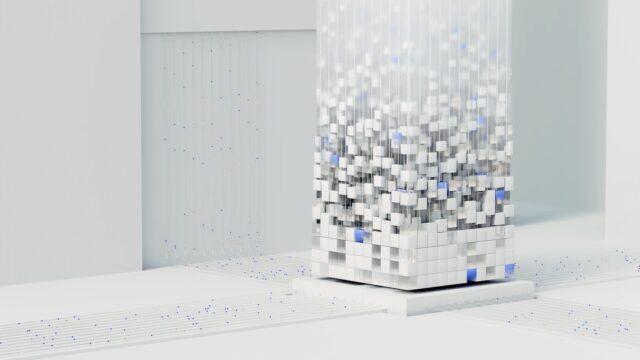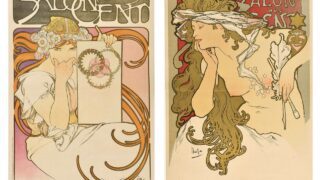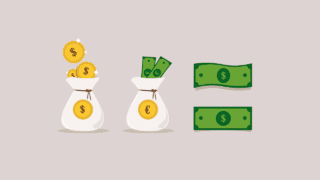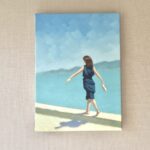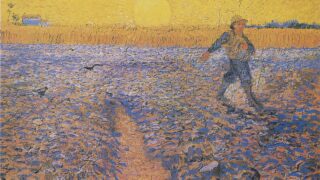もはや現代社会において、欠かすことのできないインターネット。
誰もが日常的に利用する、重要なインフラとなりました。
ところで、そもそもインターネットとは何でしょうか?
そこでここでは、知っているようで知らないインターネットの基本を、わかりやすく解説してみました。
その基本や仕組み、成り立ちの歴史、現状の課題まで詳しく見ていきますよ。
えっ本人じゃん!Audibleでは人気声優が原作のナレーションを担当!
インターネットとは何か?
インターネットとは、世界中のコンピュータ同士を繋ぐネットワークのことです。
ネットやウェブという言い方の方が、よく使いますね。
地球規模の情報通信網であり、現代における情報技術の基盤となるテクノロジーです。
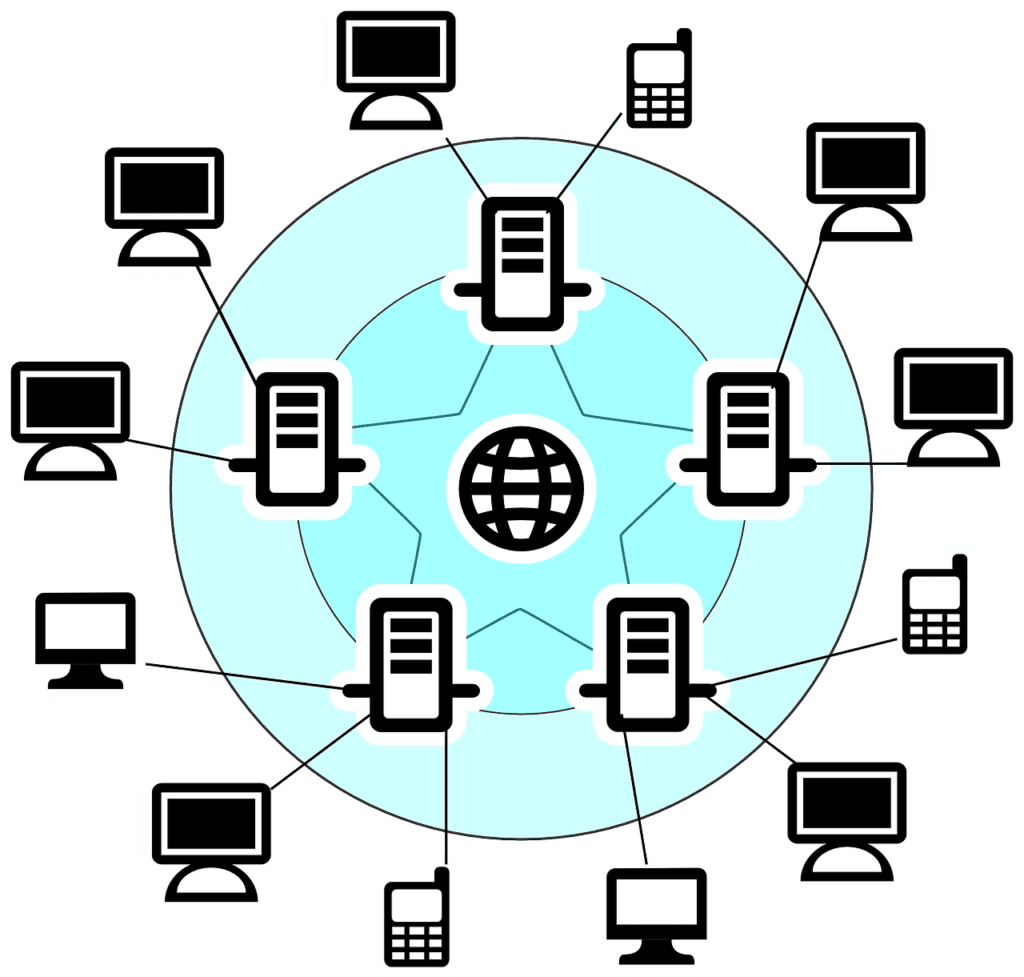
「世界中のコンピュータ同士の相互接続」とも言えます。
SNSを見ても分かるように、世界中の様々な情報が、いつでも瞬時に手に入ります。
今や重要なインフラとして、人々の暮らしを支える機能を果たしている訳です。
インターネットの基本要素
2台のコンピュータを繋げば、それもネットワークです。
インターネットとは、そうしたコンピュータネットワークの集合体です。
つまりインターネットとは、世界中のコンピュータやネットワークが相互に接続された巨大なネットワークです。
これにより、情報の送受信やコミュニケーションが可能になりました。
今や世界中のコンピュータが、そこに繋がっています。まるで、巨大な生命体の様です。
そんなインターネットの仕組みを、その基本的な構成要素から、わかりやすく解説していきたいと思います。
コンピュータ
インターネットを構成する、最も基本的な要素がコンピュータです。
コンピュータが無ければ、インターネットも存在しません。
コンピュータを相互接続して、情報を送受信するための役割を果たしているのがインターネットです。
またインターネット上におけるコンピュータは、一般的にサーバーやクライアントと呼ばれます。
サーバーは情報を提供する側、クライアントは情報を要求する側です。
◾️今さら聞けない!サーバーとは何か基本からわかりやすく解説!
プロトコル
ネットワーク間で通信する仕組みが、インターネットの仕組みそのものです。
それが、プロトコルと呼ばれるものです。
これは、通信に関する規約のことです。インターネットで情報を送受信するための、共通のルールや手順だと言えます。
あらゆるコンピュータが、この通信プロトコルを用いています。
同じ通信プロトコルを使うことで、コンピュータ同士で通信のやり取りが出来るのです。
IPアドレス、HTML、HTTP、WWWなどなど、インターネットには様々な細かい仕組みがあります。これらはすべて、この通信プロトコルに則っています。
現状ではTCP/IPという通信プロトコルが標準です。TCP/IPは、データの分割や再構築、送信先のアドレス指定などを管理します。
インターネットやコンピュータのシステムは、人間社会と少し似ているかもしれません。
体系的なルールがあることによって、高度なシステムを作り上げているのです。
IPアドレス
インターネット上のコンピュータは、一意の識別子であるIPアドレスを持っています。
例えば、192.168.0.1のような形式です。IPアドレスにより、データがどのコンピュータに送信されるかが決まります。
IPアドレスは、インターネット上の住所のようなものです。コンピュータごとに割り振られた番号です。
これにより、コンピュータがネットワーク上のどこにいるか判断できるのです。
現実社会でも、相手の住所がわからないと、手紙や荷物を送ることができないですよね。それと同じ様なものです。
ドメイン名
IPアドレスは、人間には覚えにくいので、ドメイン名が導入されました。
ドメイン名とは、人間が理解しやすい形式で、IPアドレスに紐づけられたものです。
IPアドレスの、表示上の見た目と言っても良いかも知れません。
例えば、「google.com」や「yahoo.co.jp」などがドメイン名の例です。
ドメイン名を入力すると、対応するIPアドレスに変換されます。
この変換するシステムをDNS(Domain Name System)と言います。
◾️ドメインとは何か?「IPアドレスに与えられる名前」である!
ルータ
インターネット上のデータは、複数のネットワークを経由して目的のコンピュータに届きます。
その際に情報データは、ルータと呼ばれる機器を経由して転送されます。
ルータは、データの最適な経路を選び、パケット(データの小さな単位)を宛先に転送します。
ブラウザ
ブラウザとは、ウェブサイトを閲覧するためのソフトウェアです。
ブラウザはウェブサーバに接続し、HTMLなどのハイパーテキストを読み込み、ウェブサイトを表示させます。
HTTP(Hypertext Transfer Protocol)という通信プロトコルを利用して、ブラウザとウェブサーバは通信します。
情報化された現代社会において、最も頻繁に利用されているソフトウェアと言えるでしょう。
◾️ブラウザとは何か?基本から主なソフトまでわかりやすく解説!
プロバイダ
インターネット接続を提供する企業や組織をプロバイダ(ISP)と呼びます。
プロバイダは、ユーザーにIPアドレスを提供し、データの送受信を可能にします。
ちなみにIPアドレスは、プロバイダが勝手にホイホイつくっているわけではありません。
アメリカにあるICANNという組織を中心とした専門機関によって、世界的に管理されています。
◾️今さら聞けない!アフィリエイトとは何かわかりやすく解説!
インターネットの基本的な仕組み
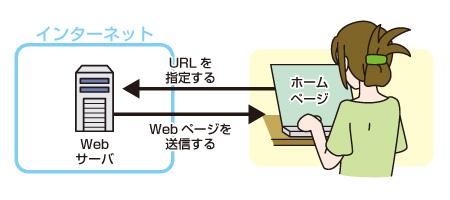
それでは、インターネットにアクセスする際の仕組みを、わかりやすく解説します。
以下が、その基本的な流れになります。
- まずユーザーが特定のウェブサイトにアクセスしようとする。例えば、ブラウザでYahooを開くなど。
- するとブラウザは、DNSシステムに問い合わせ、ドメイン名をIPアドレスに変換する。
- DNSは、リクエストに基づいて、関連するIPアドレスを見つける。
- そしてブラウザは、見つかったIPアドレスに対して、接続を確立する。
- するとユーザーのコンピュータから、ネットワーク上のルータへとデータが送信される。ルータは、データの最適な経路を選択し、次の宛先に転送する。
- そしてデータが目的のIPアドレスに到着すると、サーバーがリクエストを処理する。そして要求されたウェブページの情報を、データとして送り返す。
これを理解することで、インターネットの基本を把握することができるでしょう。
初心者にはいきなり理解するのは難しいかもしれません。
まずは先述した基本要素と、その特徴や仕組みから覚えていくと良いと思います。
社会インフラとしての役割

現在では、インターネットは重要な社会インフラのひとつになっています。
ほぼ全ての企業が、ネットを活用してサービスを売ったり宣伝したりしています。
また行政サービスも、ネットで利用できるものが増えています。
家庭においても、その重要度は大きいです。電気、ガス、水道に次いで、通信費は主要な光熱費となりました。
またFacebook、Twitter、instagram、Youtubeなどのソーシャルメディアは、今や人々の暮らしと切り離せない存在となりました。
こうしたソーシャルメディアは、人々の生活様式に多大な影響を与えました。
またAI(人工知能)の急速な進化も、人間社会を大きく変化させています。
◾️今さら聞けない!生成AIとは何かをわかりやすくサクッと解説!
インターネットの課題

インターネットがもたらした恩恵は、計り知れません。
様々な情報を共有することで、今までにない発展や進化を生み出しています。
人々の暮らしの利便性の向上に、とても役立っていると言えます。
しかし一方で、課題も数多くあります。
便利なテクノロジーには、必ず課題も同時に発生するものです。
それでは、インターネットのもたらした課題やリスクを見ていきましょう。
プライバシーの問題
インターネット上での個人情報の保護や、セキュリティの脆弱性が課題となっています。
個人情報の漏洩やハッキング、フィッシング詐欺などのセキュリティ攻撃が発生します。
個人や企業の情報が、危険にさらされることがあります。
サイバー犯罪
その拡大と共に、インターネットを利用した犯罪行為も増加しています。
オンライン詐欺、ネット上でのストーキングやいじめ、ハラスメントなどが挙げられます。
インターネット上では、日々新しい技術が生まれていますが、それと同時に、それらを利用した犯罪も生まれています。
偽情報の氾濫
インターネット上には大量の情報が存在しますが、その中には誤った情報や偽情報も含まれている可能性があります。
偽の情報を流して、大衆を操作して扇動しようとするケースもあります。
インターネットの利用においては、常に情報の正確性や信頼性を判断することが重要です。
◾️そもそもSNSとは何か?その基本から課題までサクッと解説!
時間の浪費と依存
インターネットの利用により、時間の浪費やネット依存症のリスクが生じることがあります。
特にソーシャルメディアやゲームは、その傾向が強いです。適切な自己管理が重要であり、そのための教育プログラムも必要でしょう。
誹謗中傷
ソーシャルメディアやオンラインコミュニティにおいて、ネットいじめや嫌がらせが問題となっています。
匿名性や距離の制約の少なさから、他人を攻撃する行為が増えています。
またソーシャルメディア上では、人は攻撃的になりやすく、そのため対立が生まれやすい、といったデータもあるそうです。
不安や恐怖や苛立ちといった精神的ストレスを生みやすい、というデメリットがあると言えます。
まとめ
インターネットとは何か、その基本をわかりやすく解説しました。
世界中のコンピュータ同士を繋いだ、巨大なネットワークがインターネットです。
プロトコルやIPアドレスなど、様々な技術によって構成されています。
そしてインターネットは、人々の生活に役立つ、便利なテクノロジーです。
しかし同時に、様々な問題も生み出すことになりました。社会全体で、そのあり方を常に考えていくことが重要です。
僕は基本的に、テクノロジーを敵だとは思いません。重要なのは、それをどう使って、何を生み出すかです。
インターネットはあくまで道具にすぎません。どこまでいっても中心にいるのは、それを扱う人なのです。